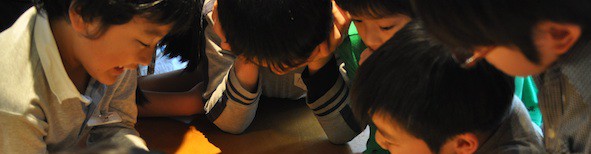こんにちは。「子どものための Critical Thinking Project」を主宰しています、狩野みきです。
いつもは critical thinking について書いていますが、今日は、この夏に出させていただいた、日向清人さんとの共著「知られざる基本英単語のルール」が増刷決定になったことを記念して(手前味噌ですみません)、この本の舞台裏と、英語の話を書かせて下さい。
そもそも私は英語教師としてのキャリアの方が「critical thinking 教師」のキャリアより若干長く、大学における critical thinking の授業も選択授業の「英語」として教えています。
「知られざる基本英単語のルール」は、英語教育者たちからの信頼も厚い General Service List(汎用性の高い単語のリスト、以下GSL)にある全2,000単語をしっかり習得してもらいたい、という願いから生まれました。GSL上の基本2,000単語をマスターすれば、書き言葉の8割、話し言葉の9割がまかなえることがわかっています。
なぜ今さら基本単語か、と言いますと、日本には、基本レベルの英単語を読解はできても、正しくアウトプットできない…という人が少なくないからです。日本の英語教育は長い間読むことに重点を置いてきたため、書いたり話したりというアウトプットの段になると「どうやって使うんだっけ」と迷ってしまう人が多いようです。
たとえば、GSLにはdiscussやfineがありますが、discuss aboutという表現は正しいか、また、fineはどういう場合に「良い」という意味になって、どう使うと「細かい」となるか、と問われると答えにつまる人はけっこういるんですね。いくら難しい言葉をたくさん知っていても、基礎部分が弱くては会話もおぼつきません。GSL 2,000語は何せ、話し言葉の9割をカバーしているのですから。
本書は、GSL 2,000単語を網羅したリアルな会話例を通して、それぞれの単語の用法・感覚・適切な文脈を効果的に身につけてもらおう、と試みたものです。2,000語の内、最重要と思われる約150語は重点的に扱われていて、会話は「励ます」「反論する」「あいさつする」などの日常の様々なシーン別に分類されています。全ての会話には、日向さんによる、学習者のツボを心得た見事な解説がついています。日向さんとの前作「知られざる英会話のスキル20」でもそうでしたが、私はもっぱら会話作成の担当です。
会話作成は「リアルな感じ」を出し、読者に読み物としても「おもしろい」と感じてもらえるかどうかがカギです。今回の本の場合は、とにかく2,000単語を会話例の中で網羅しなければならなかったので、約4ヶ月間、常にGSLリストを傍らに置いて「どうやったら効率よく2,000語を消化できるか、どうやったら自然な会話ができるか」ばかり考えていました。
実は、2,000語を消化することはさほど大変ではなかったんです。苦労したのは、①それぞれの単語の用法や代表的なコロケーション(例えばthinkとdeeplyは組み合わせて使われることが多い、などの、単語同士の慣用的なつながり)をできるだけ多く効果的に盛り込むこと、②同じ単語を同じ会話の中に何度も登場させつつ、くどいと思わせないこと、でした。コロケーションの重要度や単語のニュアンスをきちんと把握するために、日々、何種類もの辞書を広げたまま作業しました。
実際の会話をひとつご紹介しますね。astonishという動詞に焦点をあてた会話です(この会話は最終的にボツとなったものですが、ボツになっただけあって「おもしろみ」に欠けます)。
A: You astonished me! Oh … um, how was Tokyo?(びっくりしたじゃない、おどかさないでよ。ああ、そうそう、東京、どうだった?)
B: Astonishing. I was astonished to see how much the city has changed. Honestly, it changes with astonishing speed. At the same time, I was really astonished by the way they maintain their tradition. And I was astonished that there are many Chinese there.(驚いたよ。街の様子があんなに変わったのには驚いたね。正直言って、驚くべき速さで変わり続けているよ。同時に、伝統を維持しているやり方にもえらく驚いたね。それに、大勢の中国人がいるのにも驚いたな。)
使用頻度の比較的低い astonish をここまで繰り返し使う人はいないと思いますが、この会話を読んで「そうか、不意に驚かされた時にYou astonished me.と使えるのか、be astonished toとしても使えるんだな」という感覚や、適切な文脈を身につけて下されば嬉しいです。
私は会話作成の仕事が大好きなのですが(子どもと一緒に critical thinking を考えるのと同じぐらい好きです)、会話ができ上がるといつも、何度か音読します。自分で読んでみて、その会話の光景が目の前にぱーっと浮かべば「よい会話」、浮かばなければ「今イチな会話」という基準が私の中にはあります。「よい会話」の場合、光景が浮かび過ぎて登場人物と一緒に涙したり怒ったりすることもあります…ヘンですね。
最後になりましたが、「知られざる基本英単語のルール」の初版の誤植を指摘して下さった方々、どうもありがとうございました。今回の刷ではきれいになっているはずです。注意深く読んで下さる読者の存在は、執筆者にとって本当にありがたいです。今後ともよろしくお願いいたします。