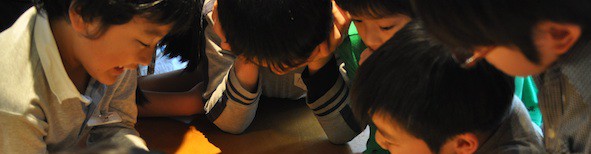こんにちは。「子どものための Critical Thinking Project」を主宰しています、狩野みきです。
守屋義彦著「かしこい子どもを育てる地アタマのすすめ」(2004年)という本については、ご存知の方も多いと思います。
小学校で長年算数を教え、現在は国立学園小学校の校長を務めている守屋氏ですが、彼の言う「地アタマ」とは、自分で考え、自分で行動し、自分の力で生き抜いていくために必要な、人間の「素地」のこと。「自分の頭できちんと考える力」を生み出してくれる根本的な能力、と言い換えてもいいと思います。
その地アタマ、なぜ今の子どもたちに必要かというと、「ひと昔前の高度経済成長期には、[だれかが先に行った道を、上手になぞって生きていくこと]も生活向上のためには必要だったのでしょう。しかし、自分たちの前に道がなく、自らが自らの道を作っていかなければならなくなったいま、この考え方には大きな問題があります」という背景のためだ、と著者は説明しています。誰かが決めた正解を探すだけではもうダメだ、というのです。
また、勉強で大事なのは「答え」そのものよりも「答え」にたどり着く道筋を自分で模索することであり、色々な物事・勉強に本当にかかわるためには「どうして?」という質問は欠かせない、子どもの「どうして?」を大切にしよう、とも守屋氏は書いています。
これは、まさに私が critical thinking を通して子どもたちに教えようとしていることと同じです。地アタマ=critical thinking のあるアタマ、とも言えるのではないか、と思いました。
私が Critical Thinking Project を通じて子どもたちに伝えたいのは、「大事なのは自分で考えること、なぜ?って考えてみること、考えるって楽しい!と発見すること」というメッセージですが、この本は、私のこのような思いは間違っていなかった、と教えてくれている気がします。
そして、もうひとつ、この本が教えてくれたのは「失敗なんて怖くない」ということです。
失敗しないように一生懸命がんばることと、失敗を怖れることとは違う — という、もしかしたら多くの人にとっては当たり前かもしれないけれど、私にとっては人生最大の課題である「問題」について、今一度考えさせられました。間違えた理由を子どもに考えさせることがいかに「失敗から学ぶ」ことにつながるか、また、子どもが転んだ時に「次はもっと上手に転ぼうね」と親が言えることがいかに大事か、この本は気づかせてくれます。
この本を読んで以来、失敗についてずっと考えていたのですが、先日、もうすぐ4歳になる我が息子がふいに「アメの絵をかいてあげる」と言ってきました。しばらく経って見てみると、床には描きかけの絵が落ちていました。「どうしたの?」と息子に尋ねると、「それ、しっぱいしちゃったの」。失敗したからと言ってしょげる様子もなく、息子は新しい紙いっぱいに無数の「アメ」を黙々と描き続けていました。
息子の「アメの絵」の完成図はリビングに飾りました。一方の、棒付きキャンデーのようなアメが3つだけ描かれた、余白だらけの「しっぱいしちゃった」絵は、今、私の目の前にあります。
大人の場合は、本当に失敗が許されない状況もあるわけですが、それでも、何か失敗した時には、「なんでかなぁ」と子どもと一緒に考えられるような親になるのが目下の目標です。失敗しても大丈夫だよ、次がんばればいいんだよ、と今日も息子の絵が励ましてくれます。