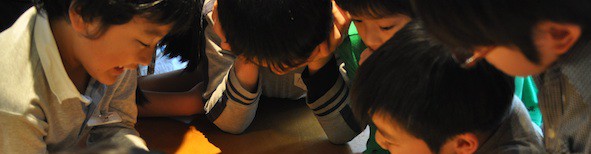こんにちは。「子どものための Critical Thinking Project」を主宰しています、狩野みきです。
昨日、ひょんなことから、美術館とは普段まるで縁のない子どもたち(8歳と3歳)を連れて「モダン・アート,アメリカン展」(国立新美術館、12月12日まで開催)に出かけました。アメリカ初の近代美術館である「フィリップス・コレクション」からの、美しい色彩の作品110点がズラリ。肩肘張らずに楽しめる、おススメの展覧会です。
子どもどころか、私自身が美術展とは縁のない生活を送っているのですが、昨日久しぶりに出かけてみて、「もっと子どもを連れて美術館に行かねば」と思いました。美術展は子どもが本物に触れられる絶好の機会でもあり、貴重な「考えるヒント」をも与えてくれます。中学生以下は無料という美術館も多いので、ある意味とてもお得です。もちろん、騒いで走る生き物である子どもに「騒がない、走らない」を徹底させ、「触らない」と言い聞かせる必要はありますが。
以下、子どもと一緒に、一流の絵画に囲まれて一流の(?)考える時間を持つための、一案です。何せ昨日思いついたことなので、まだ荒削りです、スミマセン。
- まずは、子どもが退屈していないかどうか、チェック(残念ながら、退屈しているようなら、「考える時間」はあきらめた方がいいかもしれないです)。
- 子どもが興味を持った作品に関しては、題名を教えずに「これって何の絵だと思う?」と尋ねたり、抽象画などについては、例えば「この絵が○○(例:教会)だって!なんでこんな教会を描いたんだろうね」と話し合ってみる。「無題」という作品などは、想像力を育む格好の題材になります。
- 「この中でもしも1枚だけ持って帰ってもいいって言われたら、どの絵をもらいたい?1枚だけ、自分のいちばん好きな絵を探してみようよ」と提案してみる(年齢が低い子どもの場合「本当に持って帰れるわけじゃないよ」と念を押す必要があるかもしれないですね)。
- いちばんのお気に入りを子どもが教えてくれたら、その絵の前に一緒に立ち、思い切り鑑賞。「なんでこの絵が好きなの?」と聞いてみる(ちなみに、上の子は、湖が描かれた作品を選んだのですが、理由は「水の感じがとてもすてき。水って感じがすごくする」。下の子が選んだのは全体的に水色がかった絵でしたが、理由は「水色がきれい」)。
「もしも1枚だけ持って帰ってもいいって言われたら、どの絵をもらいたい?」という問いは、私のかつての美術の先生が、美術館に連れて行って下さると決まって聞いてくれたものでした。「そうやって見ると、絵は楽しいよ」と仰っていました。当時は「この先生、変わったこと言うなぁ」ぐらいにしか思っていなかったのですが、あらためて考えてみると、この問いは奥深いと感じます。
美術展に行くと、歴史的に価値があるとか、批評家が絶賛しているとか、有名な画家によるものだとか、そういう他人による評価や知識に自分の「評価」が引きずられることが時にはあると思います。そういう知識を得ることはとても良いことだと思いますが、自分の意見が見えなくなるのは、もったいないとも思うのです。
私自身、「批評家がすばらしい作品だって言うけど、どこかいいのかわからないなぁ、良さが理解できない私がバカなのかなぁ、バカだって思われたくないから『すばらしい』って言っちゃおう」と思ったことが何度もありました。
私に傑作を理解するだけの「眼」がそなわっていなかった可能性は十二分にあるのですが、一方で、自分は本当は納得していないけれど、他人が決めた評価(=正解)をとりあえずうのみにする…というのは、「納得はいかないけれど、先生が正解だと仰るのだから正解だと信じよう」と従ってしまう「正解主義」の姿勢と同質のものを感じます。
だからこそ、(がんばって)美術展に子どもを連れて行って「自分だけのお気に入り」を探してもらうことには意義があると思っています。その作品の題名について一緒に考えたり、ある程度の年齢の子どもなら、画家について一緒に調べることもできますよね。調べ方を子どもに教えてあげるいい機会にもなると思います。
理屈はともかく。子どものうちに「本物」に触れるのは、何ものにも代えがたい経験です。皆さんも、子どもと一緒に美術館に出かけてみませんか。