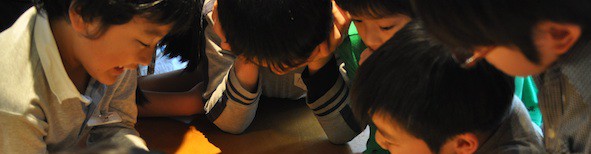こんにちは。「子どものための Critical Thinking Project」を主宰しています、狩野みきです。
先日このブログで失敗の重要性について書いたのですが、それを読んだ友人が、アメリカで最近発表になった「失敗に関する研究」について教えてくれました。失敗と脳の関係に関する、とてもおもしろい研究です(私はこれを読んで、脳科学者の茂木健一郎さんが「日本に元気がないのは失敗が許されないからだ」とおっしゃっていたことを思い出しました)。
今日はこのアメリカ発の研究内容と、その研究内容と結びついている「子どものほめ方」について書きたいと思います。
まずは、失敗と脳の関係についてです。
人間は失敗をおかすと、その直後に脳内で2つの反応が起こるのだそうです。第一の反応はネガティブな反応。ミシガン州立大学の研究報告によると、この反応は失敗のo.05秒後に起こるとか。
ところが、失敗後0.1-0.5秒経つと、今度は脳内にポジティブな反応が起きるそうです。何がいけなかったのか、などと失敗に注意をはらいだした時にこの反応が起きると言われています。
このポジティブな反応の出方は人によって様々ですが、原則、「人間、努力したってたいして成長できないよ」と思っている人よりも「がんばればもっと成長できる」と信じている人の方が圧倒的に「脳内ポジティブ反応」を多く出すのだそうです。
まずは強い脳内ネガティブ反応を出し、続けて、一貫性のある脳内ポジティブ反応を多く出す人の方が、次から間違いをおかしづらくなる、ということもわかっているようです。私は脳科学のことはよくわかりませんが、この報告を読む限り、どんどん失敗して「どうして間違えちゃったのかな」と建設的に考えることが成長の第一歩だ、ということが脳科学からもわかるということだと思います。
そして、この失敗後の「脳内ポジティブ反応」は、今日の第2のテーマ、「子どもの正しいほめ方」につながっていきます。
こちらは、スタンフォード大・心理学教授の Carol Dweck 氏らの研究が明らかにしたことですが、子どもが何か問題を解いた時に「頭いいのね」(You must be smart.)とほめられた場合と、「がんばったのね」(You must have worked hard.)とほめられた場合とでは、その後の伸び方がまるで変わってくる、というのです。
「頭いいのね」と言われた子どもは、これからも「頭がいい」とまわりから思われたいという気持ちが強くなるため、難しい問題にあまりチャレンジしなくなるそうです。間違えることによって「本当は頭よくないんだ」と思われたくないからですね。間違えることのない「安全ゾーン」にい続けようとするわけですから、学ぶことも当然少なくなります。
一方、「がんばったのね」と言われた子どもは、「がんばった」こと自体をほめられたという認識があるので、色々なことにチャレンジするようになるのだそうです。そういう子どもは当然、失敗から学ぶ率も高いようです。一方、頭の良さをほめられた子どもは、一度失敗すると「失敗したのは頭が悪いからだ」と思ってそれ以上学ぼうとしない、というのです。
おもしろいことに、頭の良さをほめられることに慣れている子どもは、「人間、努力したってたいして成長できないよ」と思う傾向があり、一方で、がんばったことを評価されている子どもには、「がんばればもっと成長できる」と信じるタイプ—つまり、失敗した後の脳内の「ポジティブ反応」がたくさん出るタイプ(失敗についてきちんと吟味するタイプ)—が多いのだそうです。
研究報告がすべて、だとは思いませんが、ちょっと考えさせられてしまいますね。