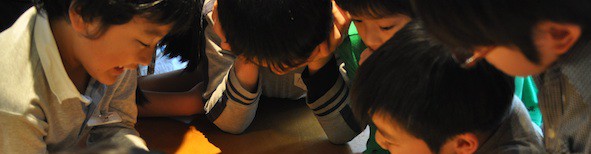<お知らせ>
・セミナー「今、子どもに必要なのは英語とクリティカル・シンキング」をさせていただきます(2012年1月)。お父さん、お母さんだけでなく、教育関係者、子どもの教育にご興味のある方、どなたでも歓迎です。託児サービス付き。詳しくは、こちらをご覧下さい。
・ワークショップ「女性のためのクリティカル・シンキング」を開催します(2012年2月)。詳しくは、こちらをご覧下さい。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
こんにちは。「子どものための Critical Thinking Project」を主宰しています、狩野みきです。
クリティカル・シンキング(以下、CTと略)を学んだことのある大人に、子ども向けCTの内容を教えると、「うそぉ、これがCT?」と驚かれることがあります。
たしかに、私自身が大人に教えている「CT」と、子どもに教えている「CT」とでは、内容がかなり違います。どう違うのか、なぜ違うのか…というのが今日のテーマです。
Critical Thinking って何?にも書きましたが、CTとは「与えられた情報や他人の意見を問い直し、そこから論理的かつクリエイティブにより良い選択肢を考えだす力」のことですが、簡単に言ってしまうと、CTとは「自分の頭できちんと考えること」です。
こう書くと、「考えること」なんてわざわざ教わらなくたって知ってますぅ、との声が上がりそうですが、ここで言う「きちんと考える」というのは「本当にこの情報は正しいのか、この人の言っていることは理にかなっているのか、他に考慮すべき問題点はないのか、と徹底的に論理的に考える」という意味です。これをなるべく少ない字数で言うと、「与えられた情報や他人の意見を問い直す」となるんですね。
では、なぜ「情報や意見を問い直す」必要があるのかというと、そうしないと、困ったことになるかもしれないからです(例:他人の言ったことを鵜呑みにして経済的に損をする場合)。あるいは、問い直すことによって、より良い「未来」が得られるかもしれないからです(例:「効果的な英語勉強法」と言われているものが本当に効果的なのか、問い直すことによって「より効果的な」勉強法が得られる場合)。
要するに、CTは机上の「お勉強」というよりもむしろ、日々の生活において「困ったことにならないために」または「より良い未来を築くために」実施するスキル、つまり、実生活を生き抜くためのスキルである、と言えます。
話を「子どものCTと大人のCTの違い」に戻しますと…この2つがなぜ違うのかというと、ひとつには、CTが「実生活を生き抜くためのスキル」だから、と言えると思います。大人と子どもの「実生活」が違うからこそCTも違ってしかるべきで、子どものCT=大人のCTを水で薄めたバージョン、という図式ではないんですね。もちろん、子どもの頭のレベル(思考力や論理力)と大人のそれとでは大きな違いがありますから、その点も多いに考慮する必要がありますが。
理屈はともかく…何よりも、私が子どもたちに体感してほしいのは、自分で「きちんと」考えることは楽しい、ということです。自分の頭で考えることがこれからの世の中では特に大事である、ということにも気づいてほしいと思っています。
私がCTを教えている大学生が先日、「私ももっと早い時期にCTを学んでおきたかった」と言ってきました。Better late than never.(遅れても何もしないよりはマシ)ではありますが、一方で The earlier, the better. (早ければ早いほどいい)とも言えると思います。