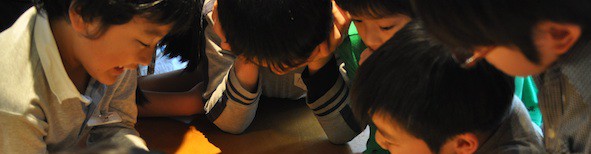☆ 子育て用のムック(学研)に「子どもの思考力・自己肯定を育む声がけ」にまつわる狩野の話が掲載されます。発売は3月末予定です。お楽しみに!
☆ 小学生の考える力と伝える力を伸ばすコミュニケーション能力プログラムの初級クラス(2期生)および上級クラス(1期生)は2月24日よりスタートです!
☆ Wonderful☆Kidsは、子どもたちの考える力を伸ばし、「生きる力」を伸ばすスクールです。
——————————————————————————————————————————————
こんにちは。Wonderful Kidsの狩野みきです。
『頭が柔らかくなる算数』(日経プレミアシリーズ)については、先日フェイスブックページでもご紹介しましたが、この本には、子どもとワイワイ言いながら思わず解きたくなってしまう「算数の問題」がたくさん載っています。
著者のお一人である守屋義彦氏(国立学園小学校校長・附属かたばみ幼稚園園長)は、去年の末、IWCJさんと私とで立ち上げた「子どもの考える力教育推進委員会」のメンバーにもなって下さっています。守屋先生の本書内のコラムには「優秀な子どもというのは、自分の考えを捨てられる子どもです」とあります。友だちが算数の問題で別の解き方をしてみせたときに、どうしてボク・私はそれに気づかなかったんだろう、と自分の考えを捨てて柔軟に色々な考え方ができることがすばらしい、と。
自分の考えを一時的に捨てて、他の考え方にも進んでチャレンジする。大人でも難しいことですよね。
そして、この本のもうお一人の著者、山梨大学教授・中村享史氏が書いていらっしゃることも、とても心に響きます。
「さらに大事なのは、音楽鑑賞や美術鑑賞と同じように、ほかの人の解決方法を鑑賞し、なるほどおもしろいな、いいなと思える心を育てることです」(『頭が柔らかくなる算数』より)
ここでいう「解決方法」とは算数や数学の問題の解き方のことですが、それにしても「鑑賞」とはなんとステキな言葉でしょうか。
「鑑賞」とは、「芸術作品などを見たり聞いたり読んだりして、それが表現しようとするところをつかみとり、そのよさを味わうこと」(大辞泉)です。他の人の解き方を見てきちんと理解し、「わあ、すごいな、おもしろいな」と素直に感動することのできる心…そのことを中村氏は言っているのですよね。
今週末から、小学生対象の「コミュニケーション能力プログラム」の1期生・上級クラスと2期生・初級クラスがスタートします。
このプログラムで重視するのは、子どもたち一人一人の考えや意見です。どんな意見だって、一生懸命考えればOK!というポリシーのもとに、子どもたちのすばらしい想像力や論理力が花開いていきます。
子どもたちには是非、他の友だちの意見を鑑賞できる心を育ててもらいたいです。自分の考えに執着せずに、色々な可能性を素直に認めて「すごいね、おもしろいね」と互いに言い合い、考えることを楽しめる場。そんな場を作っていきたいと思います。
☆コメントはこのサイト上のコメント・ボックス、あるいは、Wonderful☆Kidsのフェイスブックページに寄せていただけるとたいへん嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。